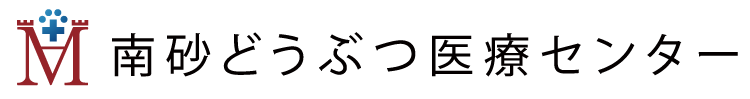肝臓疾患

肝臓外科が必要な症例に対してはCTにて該当部位の特定や周囲組織への播種を判断し切除可能なラインがどこなのかを判断し計画を立てる。
胆嚢疾患

犬の胆嚢粘液嚢腫について
みなさんは胆嚢粘液嚢腫(たんのうねんえきのうしゅ)という病気をご存知ですか?
飼い主様にとって少し聞きなれない病名かもしれませんが、実はこれ、犬ちゃんにとってかなり怖い病気です。
症状が表に出にくい病気ですので、気がついた時には外科手術による治療が必要なほど進行してしまっていることも。
早期発見には定期的な健康診断が重要です。
今回は、犬の胆嚢粘液嚢腫について紹介し、早期発見の重要性や日常で気を付けるべきポイントなどをお話しします。
胆嚢粘液嚢腫とは
胆嚢は肝臓で作った消化酵素(胆汁)を濃縮して貯める臓器で、必要に応じて胆汁を消化管に排出します。
通常であればサラサラしている胆汁ですが、胆嚢粘液嚢腫では硬めのゼリーのようになり、胆嚢内に留まって胆嚢を圧迫します。
悪化すると胆管肝炎や総胆管閉塞、胆嚢破裂などのリスクが高まります。
胆嚢粘液嚢腫の原因
本病ははっきりとした原因は判明していませんが、高脂血症(肥満)や胆泥が胆嚢に溜まることなどが原因になり得ると考えられています。
このため、高脂血症を起こしやすい以下の犬種での発症が多いとされています。
- シェットランドシープドック
- アメリカンコッカースパニエル
- ミニチュアシュナウザー など
※これ以外の犬種であってもなりうる病気です。
また、甲状腺機能低下症や副腎皮質機能亢進症などの病気との関連も推測されています。
胆嚢粘液嚢腫の症状
胆嚢の病気は初期症状が出にくく、普段の生活では気がつかないことが多いのが特徴です。
このため、健康診断で偶然見つかることも少なくありません。
総胆管閉塞になると黄疸(目や皮膚が黄色くなる)、嘔吐や下痢などの症状が出たり、明らかにぐったりしてご飯を食べなくなったりします。
さらに胆嚢が破裂しお腹の中に飛び散った胆汁によって重度の腹膜炎や膵炎が起きると、急に体から力が抜けてぐったりするショック症状や、発熱なども認められます。
※異常に気づいた時点ではすでにかなり進行していることがあります。
ぐったりしていたり黄疸が出ていたりする時は、様子を見ずに早急に受診しましょう。
胆嚢粘液嚢腫の診断
症状は見える部分には出ませんが、血液検査で肝臓の数値に異常が出ます。
診断は超音波検査で行います。
超音波検査では胆嚢内部がキウイの輪切りのように見えます。この特徴的な所見が胆嚢粘液嚢腫の診断基準になります。
胆嚢粘液嚢腫の治療
内科的に胆汁の排泄を促すこともありますが、基本的に外科手術以外に根治させる方法はありません。手術では胆嚢を摘出します。
犬の年齢や基礎疾患の有無によって手術のリスクは異なるので、必ずしもすぐに手術になるわけではなく、基礎疾患の治療を先に行うこともあります。
なお、総胆管閉塞や胆嚢破裂などでは、ほとんどの場合、緊急手術が必要です。
日常で気を付けるべきポイント
胆嚢粘液嚢腫は比較的新しい疾患ですので、病態や予防法・治療法についての統一した見解がないのが現状です。
胆汁の排泄がうまくいくように、食生活に注意してあげることが予防につながるかもしれません。
食生活で胆汁の分泌を促すには・・・
- 脂肪分の多すぎる食事は控える
- だらだらぐいなどの食生活の乱れに気を付ける
- 運動不足にならないようにする など
また、すべての病気に言えることですが、早期発見と早期治療は重要です。
定期的な健康診断を実施し、症状の出にくい本病を早期に発見できるようにしましょう。
※なお当院では胆嚢外科は即日手術が可能です 紹介病院の獣医師は手術見学も可能です。