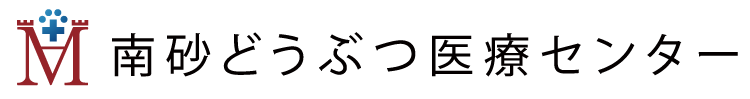尿管結石
猫の尿管結石について
尿管閉塞を起こさないよう、普段と様子が異なればすぐに受診を
尿管は腎臓から膀胱へおしっこを運ぶ管のことで、この管内に発生した結石のことを「尿管結石」といいます。猫で比較的よくみられる病気ではありますが、最悪の場合死に至ることもあるため、万が一に備えて正しい知識を持っておくことが大切です。そこで今回は、猫の尿管結石について解説していきます。
症状
猫に尿管結石ができると血尿や頻尿といった膀胱炎のような症状がみられますが、なんとなく元気や食欲がないだけで目立った症状がみられないケースもあります。
ただし、結石が尿管を塞いでおしっこが完全に出なくなってしまうと(尿管閉塞)、尿毒症を起こして死に至ることもあります。
原因
猫の尿管結石の原因としては、以下のようなものが挙げられます。
- 食事内容
- 飲水量の減少
- 肥満
また、アメリカンショートヘアーやスコティッシュフォールド、ヒマラヤンでの発生が多いという報告があり、遺伝的な要因が関係しているのではないかとも考えられています。
診断方法

猫の尿管結石は以下のような検査を行い、診断します。
- 尿検査:腎臓の機能や結晶の有無・種類などを確認します
- 血液検査:腎臓の機能や全身状態を確認します
- レントゲン検査:腎臓の大きさや結石の有無を確認します
※猫の尿管結石はかなり小さいため、レントゲン検査では確認できないこともあります - 超音波検査:腎臓や尿管の状態、結石の有無、閉塞の有無などを確認します
また、場合によっては造影検査やCT検査など、さらに詳しい検査を行うこともあります。
治療方法
尿管結石の治療方法には、内科的治療と外科的治療の2種類があります。しかし、点滴や薬を使って内科的に結石を自然排泄できるケースは少なく、多くの場合は外科的治療を行います。
外科的治療には、さまざまな手術方法があります。
- 尿管切開による結石の摘出
- 尿管の移設
- ステントの設置
この他にも、当院では人工尿管を体内へ設置する「SUBシステム手術」を行っています。SUBシステム手術は、手術後も定期的に管を洗浄する必要があるものの、手術時間が短いことや再発のリスクが低いといったメリットがあり、大切な愛猫の命を救うための有効な選択肢の一つです。
当院での症例も溜まってきておりますので、お気軽にご相談ください。
予防方法
気温が低くなる冬や高齢猫では飲水量が少なくなる傾向にあるため、水飲み場の数を増やしたり自動給水器を活用したりして、なるべく水をたくさん飲めるような工夫をしましょう。
また、運動不足は肥満や飲水量の減少などを引き起こすため、キャットタワーを使って上下運動をさせたり、おもちゃを使って運動量を増やしたりして、運動不足に陥らないように気をつけましょう。
まとめ
猫の尿管結石は比較的よくみられる病気ですが、尿管閉塞を起こしてしまうと命を落としてしまうこともあります。目立った症状がみられないケースも多いため、日頃からよく愛猫の様子を観察し、いつもと何か違うと感じたらすぐに病院を受診するようにしましょう。
従来の診断手技に加えCT検査も可能なことより腹部の毛刈りやエコーゼリーでのエコー検査でも判別の困難な症例での結石(数ミリ単位以下)までの診断が可能
※当院では即日外科手術可能です。紹介病院の獣医さんの見学も可能です。
かかりつけ医やそこからの紹介病院にてこの数値では無理ですと言われてもあきらめないでください。
CRE(クレアチニン)18数値レベルの子でも受け入れています。
腹膜透析
ワンちゃんネコちゃんの急性腎不全に対して腹膜透析を行っております。
透析には血液透析と腹膜透析があげられます。血液透析は高価な透析装置を利用する必要があり、頸静脈へ太い径の血管確保が必須であります。
また透析で循環する血液量は体重8kgの個体でも30ml程度の例もあり、機械への血液のロスがありますので腎性貧血の貧血がすこし進行するケースがあるようです。
以上より当院では腹膜透析をより推進しております。
当院では急性腎不全の症例に対して腹膜透析を実施しております。
鎮静は必要ですが透析チューブ設置は15分程度で可能です。
透析液の浸透圧を利用し尿毒素を尿で排泄できない子に対して透析液へ排泄を促す治療となります。